シングルマザーの手当

目次
ひとり親家庭の世帯数
※厚生労働省発表
平成24年までの情報ですが、現在はもっと増えているとされています。

私は2児を持つシングルマザーですが、母子での生活になって初めて知った手当も多かったのでご紹介したいと思います。
母子家庭への手当
⑴児童手当
児童手当
中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
【児童手当の金額】
・0歳~3歳未満の児童…1人月額1万5000円
・3歳以上~小学校6年生までの児童で第1子、第2子…1人月額1万円
・3歳以上~小学校6年生までの児童で第3子以降…1人月額1万5000円
・中学生の児童…1人月額1万円
児童手当は、母子家庭に限らず子供がいる世帯がもらえる手当ですね。
⑵児童扶養手当
児童扶養手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を養育している方
【児童扶養手当の金額】
・1人目…全部支給4万1020円(一部支給4万1010円~9680円)
・2人目…5000円加算
・3人目以降…1人3000円加算
児童扶養手当は受給者の方の所得によって支給される金額が異なる場合がありますので、事前に市役所などに相談すると良いでしょう。
⑶特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を養育している方
【特別児童扶養手当の金額(平成26年4月分から)】
・1級:4万9900円
・2級:3万3230円
所得制限限度額を超えるときは支給されません。離婚後に所得が減少する場合にはそれほど気にする必要はないかもしれませんが、市役所などに確認することをおすすめします。
⑷ひとり親家族等医療費助成制度
ひとり親家族等医療費助成制度の対象
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童及びその児童を監護する母もしくは父、又は父母以外の養育者で、国民健康保険や健康保険などに加入している一定所得基準未満の方
【医療費助成の内容】
・医療費
ひとつの医療機関ごとに1日最大500円までの負担となります(3日目以降の負担はありません。)
なお、複数の医療機関にかかる場合は、ひとつの医療機関ごとに1日最大500円の負担となります。同じ月に負担した医療費が2500円を超えたとき、申請をすると超過分の払い戻しを受けることができます。
・入院時の食事療養費及び生活療養費の標準負担額
食事療養費(食事代)の自己負担はありません。
・訪問看護
助成の対象ではありません。
通常だと費用がかかるので病院も負担になりますが、医療費の助成はとても助かります。
⑸母子・寡婦福祉優遇制度
児童扶養手当などの母子手当や補助などをもらうことも非常に重要ですが、割引や免除を受けることは、母子手当をもらうことと同じように大切なことです。
・市営交通の料金の福祉割引
・水道料金・下水道使用料の福祉減免
・駐輪場利用料金の割引
・JR通勤定期の特別割引
・所得税・市府民税の軽減
⑹国民健康保険の免除
世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯について、所得の金額や世帯の人数によって国民健康保険の免除を受けることができます。
⑺国民年金の免除
前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが難しい場合は、所得の金額や扶養親族の人数によって国民年金の免除を受けることができます。
⑻養育費
都道府県や市町村の児童扶養手当や助成制度だけではなく、養育費もしっかり確保することが重要です。
母子家庭の手当だけでは、それほど大きな金額にならない上、就業で大きな収入を得ることも難しい母子家庭が大半なのが現実です。
養育費の確保は非常に大きく重要なことなのです。
養育費をしっかり確保するためにも、公正証書の作成をおすすめします。
※手当内容は、都道府県によって多少違う場合があるので、お住まいの地域で確認が必要です。
ご紹介したように、現在は手当も多くなりシングルマザーも生活がしやすくなっていると思われがちです。
しかし、現実としてまだまだ問題も多く、母子家庭の貧困も深刻な問題となっています。

子育てしながら仕事、家事をこなす。
シングルマザーに限らずこうしたワーキングマザーは、現代非常に増えています。
次回も続けてお話ししていきますね。












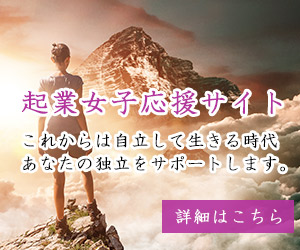
この記事へのコメントはありません。